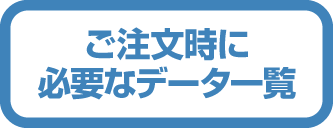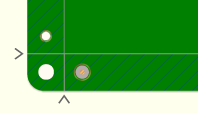Vol.034 プリント基板の達人
< 第2回 >
基板設計の初期段階での注意点について
皆さん。こんにちは。(有)実装彩科の斉藤です。
今回は基板設計においてパターンの引き回し、アナログとデジタルの違い、
高周波・シミュレーション関連についてお話したいと思います。
前回、「機能試作」、「製品試作」、「量産試作」の違いについて触れました
がご記憶に残っていますでしようか。
何か電子回路を目に見える形にするには先ず「機能試作」を行います。
この段階では、ラグ板に部品をはんだ付し、それらを線材でつなぐ。
あるいはユニバーサル基板を使う。
さらには、以前作った製品基板の一部を糸ノコで切り取って再利用するなど
荒業をやっている方もおられるかもしれません。
いずれにしても、部品間を線材でつないでいる状態をよりコンパクトにする
ためにプリント基板が登場する訳です。
この線材に相当するのが、プリント基板で言うパターンで、2層以上の基板
ですと各層をつなぐスルーホールもあるのでこれも線材の一部に相当すると
考えて良いでしょう。
今回は基板設計に関するテーマなので、その線材をどのようにパターンに置き
換えるかということになります。
ここで一寸想像していただきたいのですが、今、適当に部品間をつないだ線材、
とりあえず、電気が通れば良いということで、その辺に転がっている線材を
あまり深いことは考えないで使ったかも知れません。
しかし、電気を通すからにはその電流の大きさによって線材の電気抵抗により
ジュール熱が発生し、あまりにも細い線材に大きな電流を流すと溶断してしま
います。
プリント基板のパターンも銅で出来ていますので、同じことが起こります。
最悪、火災になるので要注意です。
したがって、基板設計の基本の一つとしてパターンの断面積に対してどれだけ
の電流を流すのかを決めなくてはいけません。
これを決めるのにはIPC2221Aのモノグラフがルーツですが、国内では例え
ばJPCA規格 PB01-2004 図33等を参照すると良いでしょう。
通常のパターン断面の厚さは、スルーホールめっき厚を加えても45~60μm位
ですが、特殊電源やフォークリフトのバッテリー制御用基板などでは105~
210μmある大電流基板も存在します。
最大500μm以上というものも聞いたことがあります。
このパターンの厚さが厚いほど基板は作りにくくなります。
その理由は基板製造プロセスのテーマに譲ります。
さて、基板設計自体の話に戻します。与えられた面積の基板にどのように部品
を配置するか。
これには結構なノウハウがあります。
基本的には回路図の信号の流れのとおりに部品を配置するということになって
いますが、およそ100MHz以上に信号伝送スピードが速くなると基板自体の浮遊
容量、ノイズの問題で単純に部品の端子間をつないだだけでは信号がうまく伝
送できなくなります。
また、バスラインについては全てのパターンの長さを同一に設計して、信号の
伝送タイミングを一致させないといけない場合もあります。
これらに関連するノウハウは数々の著書が出ていますのでこのシリーズでは詳
細には触れないことにします。
ところで、基板の製造面のみを見てみますと、実際の基板の仕上がりのパター
ンの断面形状はきっちりとした矩形にはならないので設計誤差が生じます。
また、多層基板の場合、層間の寸法も設計値に対してばらつきが生じるので、
設計仕様どおりの性能が出ないということが生じます。
そこで最近では開発期間を短縮するため、過去の経験値を織り込んだシミュレ
ータを用い、実際に基板を作る前に色々検証することが主流になっています。
この経験値をどの位正確にシミュレータに入力しているかが技術力の差になり
ます。基板設計と製造を同一の基板メーカでやっている場合は、各製造ロット
のプロセス条件に対して、実際のプリント基板がどのような形に出来たのか、
バターンの断面形状を計測してデータの積み上げを行っています。
実にコツコツとやらねばならない地味な作業ですが、これが高度なものづくり
そのものに通じているといえるでしょう。
いままでお話したことは基本的に線材に替えて端子と端子を「単純につなぐ」、
つまりパルス信号をデジタル回路設計でイメージしていますが、回路には連続
的に信号の大小が変化するアナログ回路もあります。
とりあえず、ラジオをイメージしてください。音は連続的に変化しますね。
これを信号に置き換えたものととらえてください。
アナログ回路は、高周波領域のデジタル回路と同様に雑音や干渉など外部要因
に弱い、部品(素子)のばらつきに影響されやすい、回路自体が比較的に簡単な
ので逆に複雑な処理を出来ない という特徴があります。
そのために、デジタル回路基板は基本的には単一な線幅のラインで端子と端子
をとりあえずつなげば良いことに対し、アナログ回路基板はそうはいかず、
銅パターンの面積自体が回路の定数のような取り扱いになったりします。
同時にアースとする銅パターンの形状をどのようにするかも大きなノウハウに
なります。
そこで両者のパターンの形状の特徴を概観すれば、デジタル回路基板では直線
のラインが平行に配置されている基板設計になり、アナログ回路の基板ではラ
インは自由曲線だったり、べたパターンの形状も丸みをおびた形になります。
衛星放送の平面型受信アンテナを想像してください。
樹脂のカバーを外すと、その中はべたパターンに単純な形状のスリットを入れ
ただけの基板が現れます。
いたって簡単な基板に見えますが、実は回路の特性を出すために綿密なシミュ
レーションを行ってパターン設計が行われています。
基板設計で部品を配置する際、部品の発熱についても注意の必要があります。
パワートランジスタなど大きく発熱する部品を一部に集中して配置すると、
放熱が追従できなくなり、基板が焦げたり、はんだ継ぎ手にクラックが入る
不具合が生じます。
したがって、最近ではやはり製品試作時にシミュレーションにより、発熱に
ついての検証が行われる場合があります。
プリント基板に用いる基材は難燃性についての幾つかのグレードがあり、
ポピュラーなガラス布エポキシ基材(FR-4)でも、基板表面の最大持続温度を
100℃以下に抑えるような放熱対策を講じないと長期信頼性に不具合が
生じることがあります。
部品配置といえば、部品自体の重量の分散設計にも注意する必要があります。
大型電解コンデンサ、フライバックトランス、放熱器など質量が重たい部品を
基板に搭載する場合は、経験値として1本の部品リードに7g以上の力がかか
らないように部品自体を補助的な支持体で保持する必要があります。
そうしないと、「クリープ」といって静的な持続加重がリードにかかりはんだ
継ぎ手から部品リードが抜ける不具合が生じます。
さらに重たい放熱器をアースと共用する場合、基板に連続的にあけた穴に
放熱器の一部を挿入してはんだ付けすると穴の間にクラックが入り、さらに
クラックがパターンを断線させる不具合が生じるときがあります。
各穴間の間隙は板厚の少なくとも2倍以上取らないといけません。
また、部品重量にもよりますが、可搬機器に重たい部品を実装する設計は持ち
運びの際、テーブルなどに置いたときのGが部品重量をより重くし、クラック
を進展させることがあるので注意が必要です。
最近では同一基板にアナログ・デジタル回路を混載したものも見かけますが、
避けられるのであれば2枚の基板に分けるべきです。
コスト低減のため、2枚の基板を一枚化にするというのは理解できますが、
同一面に銅箔の多い、少ない部分が不均一な形で存在することになり、基板
製造でのエッチング条件を難しくする一方、基材の銅はくとエポキシの熱膨張
係数が異なるためにいびつな形でそりが生じます。
そりの発生は自動部品挿入・装着機の適用を難しくするばかりでなく、表面
実装部品を実装する場合はんだ継ぎ手に異常が生じます。
経験値ですが、上反りの場合90mmスパンあたり2mm以内に抑えないと長期間の
間にはんだ継ぎ手にクラックが生じます。
ここで、部品・ラインの配置について根本的な内容について触れます。
「基本格子」というものがあります。
プリント基板をパッと見たとき、沢山のラインや穴が見えますが、無秩序に
配置されているのではなく「基本格子」つまり碁盤の目の上にそれらが配置
されています。
基本格子にはミリ格子とインチ格子というものがあります。
前者の格子ピッチは2.5mm、後者は2.54mmです。
使い分けですが、挿入タイプのICを多用する場合は、そのリードピッチが規格
で2.54mmと規定されているのでインチ格子を用い、そうでない場合はミリ格子
を使うことが多いです。
ここで大切なのは同一基板において、ミリ・インチ両方の基本格子を混在させ
ないということです。
2.5mmあるいは2.54mmの大きさの格子を第1格子と呼び、その1/2にしたピッチ
の格子を第2格子、さらにその1/2を第3格子と呼びます。
また、その1/2は第4格子です。
したがって、ミリ格子の第4格子のピッチは0.3125mmになります。
原則として穴とランド及びラインはこの格子の上に配置されます。
もし、異なるピッチの格子を混在させると、10年位以前では格子と格子が
接する界面でピッチ間に誤差を生じ、CAD上でラインが繋がらないことがあり
ました。
最近のCADはこの問題については自動補正で見かけスムーズに異種格子でも
つなげられるようになっていますが、逆に、基本格子のピッチ寸法を任意に
設定できるため基板製造の現場では一寸困る場面も出てきています。
よく基板仕様を表すものとして「ライン/スペース」と書いてあるカタログ等
を見たことがあると思います。これは、導体幅(L)と導体間隙(S)を示すもの
ですが、両者の値を同じ値にしてしまった時に不具合が多く発生します。
例えばピッチ0.2mmの格子を設定し、L=0.1mmのラインを設定すれば、
Sは帰納的に0.1mmになる場合です。
基板製法には大きく分けて、サブトラクティブ法とアディティブ法があり、
大半の基板メーカが前者採用しています。サブトラクティブ法での歩留まりを
上げるには導体幅よりも導体間隙の方を広くとるというノウハウがありますが、
基板設計をされる方はこのノウハウを時とぎ見落としていることを見かけます。
ところで、このシリーズは「試作と量産の違いについて」という切り口で話し
を始めましたので、その関連でラインの配置について触れます。
よく目にするのが「パターンの引き回しのセンスのない基板」です。
試作の時はとりあえず繋がっていれば良いという感覚で、ラインの流れ方向が
統一されていないものです。平行してラインを並べていると思えば突然45°
方向へ延々と配置してある。
別の領域では-45°方向にラインが引かれているというような事例です。
これはエッチング時のラインの仕上がり精度を低下させる原因となり、周波数
が高い基板ほど避けなければなりません。
次に多いのは、先ほど基本格子の話をしましたが、スペースが沢山余っている
にもかかわらず、第4格子の最も狭いピッチにラインを10本、20本と引いている
事例です。
そうかと思えば、20本のラインから相当距離の間に何もなく、突然0.1mm位の
細いラインが大海原に1本通っているような事例です。
この場合、エッチング時に大海原の方はより多くのエッチング液に接触する
のでオーバーエッチングとなり細ってしまいます。
スペースが余っているならば細かいピッチで細いラインを並べなくとも、もう
一段階上の基本格子を用いてより太いライン幅を採用することが、歩留まりを
上げることができ信頼性的にも望ましいです。
実際にラインを配置する場合は、どの位の面積で全ての部品を接続できるか
予想しにくいので、最もピッチの狭い格子を適用した結果スペースが余って
しまうという事例です。
「製品試作1」位まではこの状態でもやむを得ないと思いますが、量産試作を
行う製品では、完全にこの段階では配線の引き回しを美しくなるように修正
しておかないとなりません。
そうしないと、あとで色々なトラブルの原因となります。
これまではラインについて見て来ましたが、穴の配置についても見てみましょう。
穴の配置位置もミリ格子、あるいはインチ格子の各交点となります。
もし両方の格子を混在させた基板を設計してしまうと、基板メーカーでユニバ
ーサル電気チェッカを用いて通電検査するときに問題が生じる場合があります。
電気チェッカの接触ピンが花を生けるときに使う剣山のように配置されていて、
このピンのピッチがミリかインチのどちらかであるため格子を混在させると
一部分が検査出来なくなるからです。
ただ、最近の検査機はやはり技術の進歩でフライングプローブチェッカという
方式、つまりテスタで端子を一つずつ当てる機能を自動機で高速に行う装置が
開発され、問題は解消の方向にはあります。
とはいっても、出来るだけシンプルな設計にすることが望ましい訳です。
このような形で「製品試作1」を実施します。
つまり、プリント基板を作り、実際に部品を実装して性能を評価します。
その結果、色々なノイズが混入してしまい、うまく予定した性能を発揮できず
にまた、試作のやり直しというようなことが起こります。
プリント基板を作るためにはフィルム原版というものが必要ですが、
原則として試作のたびに作り直さねばならないので開発費を圧迫します。
フィルム原版を作るまでにも色々な作業があるのですが、今回はこの位に
致しまして次回、この続きをお話したいと思います。